
「しんどい毎日は、一体いつまで続くんだろう…」
仕事と育児の両立に追われ、体力も精神も限界…。先が見えない不安に、本当に疲れてしまいますよね。
ワーママの大変さは「〇歳で終わり」という単純なものではありません。ですが、子どもの成長ごとに現れる「しんどさの質」は変わり、その「壁」には必ず終わりがあります。
この記事では、子どもの年齢別に、しんどさの質がどう変わるかを解説します。そして、しんどさを軽くするコツや、根本解決としての「フルリモート」という働き方までご紹介します。
もし、対策を知らないまま耐え続けると、心身がすり減るだけでなく、大切なキャリアや「自分らしさ」まで諦めることになるかもしれません。
「しんどい」を「希望」に変えるヒントを、ぜひ見つけてください。

仕事と育児を両立させる中で、多くのワーママが感じる負担のピークは、残念ながら一度ではありません。
ワーママが感じる「しんどい」という気持ちは、子どもの成長段階によって、大変さの種類が変わっていくことになります。
しかし、それぞれの時期の特性と終わりを理解しておくことで、見通しを持って乗り越えられるかもしれません。それぞれの時期で感じる「しんどさ」について説明します。
0〜2歳児期は、ワーママの「体力的しんどさ」がピークを迎える時期です。夜泣きや授乳による慢性的な睡眠不足のまま、仕事復帰するケースも少なくありません。
常に目が離せない育児に加え、保育園からの急な発熱呼び出しもワーママを悩ませます。仕事の中断や同僚への申し訳なさも重なり、心身ともに余裕がなくなってしまう状態です。
この体力勝負の時期は、子どもが2歳を過ぎ、夜間の睡眠や体力が安定してくると、最初の大きな山を越えることができます。
3〜5歳は、体力的な負担が減る代わりに「精神的」なしんどさが増す時期です。「イヤイヤ期」の自己主張がピークを迎え、とくに多忙な朝は、子どもの抵抗に焦りが募るかもしれません。時間通りに進めるための交渉力と忍耐が求められます。
また、保育園行事の準備やお弁当、持ち物への名前書きといった「細かな育児タスク」も増加します。休日に活発な子どもと遊ぶ体力も必要です。
この精神的な負担は、子どもが言葉で気持ちを伝えられるようになる5歳頃から、徐々に落ち着いていきます。
6〜8歳は「小1の壁」という新しいしんどさに直面します。最大の要因は、保育環境の変化です。保育園と比べて下校時間が早く、学童保育の利用が必要になるでしょう。
しかし、学童は預かり時間が短い場合や、長期休暇中はお弁当が必要になるなど、新たな負担が発生します。さらに、毎日の宿題チェック、配布プリントの管理、PTA活動など、親が対応すべきタスクも一気に増加します。
子ども自身も新しい環境で不安定になりがちなため、心のケアも重要です。このしんどさは、親子ともに新しい生活リズムに慣れるまで続きます。
9歳以降になると、子どもの自立が進み、体力的なしんどさや時間の制約は大きく軽減されます。急な発熱による呼び出しも減り、ワーママは仕事に集中しやすくなります。
しかし、ワーママの負担は「心のサポート」へと移行します。「9歳の壁」と呼ばれる学習面でのつまずきや、思春期に入り複雑化する友人関係など、新たな悩みが出てきます。
子どもが悩みを話しにくくなるため、ワーママには変化を察知し、じっくりと話を聞く「心の余裕」が求められます。物理的な負担から、子どもの内面に寄り添う精神的なサポートへと、しんどさの質が変わる時期です。
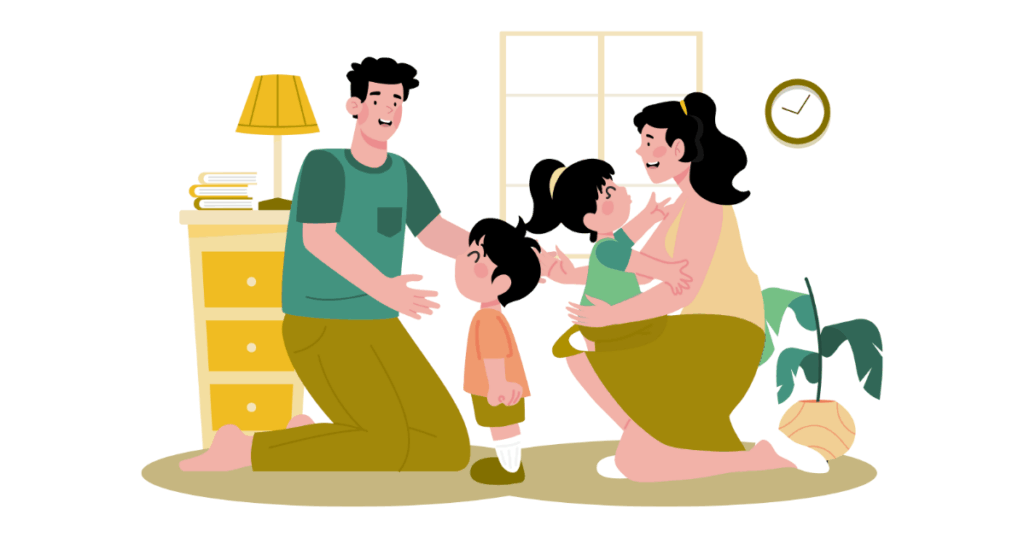
ワーママの「しんどい」を根本的に減らすためには、精神的な負担、時間的な負担、物理的な負担をそれぞれ軽くしていく工夫が欠かせません。
大切なのは、「すべてを一人で完璧にこなそうとしない」ことです。ワーママも一人の人間であり、時間も体力も有限です。
自分一人で抱え込まず、考え方を変えたり、便利なものや人の手を借りたりすることで、心と時間に「余白」を生み出すことができます。
ここでは、ワーママの「しんどい」を減らすために、今すぐ見直したい4つの具体的なポイントを解説します。取り入れやすいものから試してみてください。
「仕事も育児も100%」という完璧主義は、しんどさの大きな原因です。しかし、気持ちや意識だけで「完璧主義をやめる」というのは困難かもしれません。
そこで「仕組み」を取り入れましょう。日常のタスクを「絶対やること」と「余力があればやること」に分類します。
次に「絶対やること」の合格ラインを具体的に決めます。合格ラインは70点でも構いません。大切なのは、「絶対やること」さえ完了すればOKとして、自分を許すことです。
| タスク | 絶対やること | 余力があればやること |
|---|---|---|
| 平日の夕食 | ・主菜が1品あり、家族が食べられる状態 ・冷凍食品、総菜、ミールキットの活用OK | ・一汁三菜、栄養バランスを考えた手料理 ・品数を揃え、彩りもきれいにする |
| 洗濯 | ・洗濯機を回し、乾かす ・翌日に着る服が乾いていればOK | ・乾いた服をすべて畳む ・家族全員のタンスにしまう ・アイロンがけをする |
| リビングの掃除 | ・安全に歩けるよう、床に落ちた物を拾う | ・机の上をさっと拭く ・掃除機をかける ・おもちゃを所定の場所に戻す |
| お風呂 | ・子どもを洗い、自分もシャワーを浴びる | ・湯船にお湯を張り、ゆっくり浸かる ・浴槽をしっかり磨き、排水溝の髪の毛を取る |
生活スタイルに合わせて、「これは絶対に必要」「これは週末でもいい」というラインをご自身で決めることが、しんどさを減らすための「仕組みづくり」になります。
家事の負担を物理的に減らすため、「時短」に投資しましょう。有効なのは「家電に任せる」ことと「サービスに頼る」ことです。
ドラム式洗濯乾燥機、ロボット掃除機、食洗機などの時短家電は、長期的な時間のリターンを生みます。また、家事代行やミールキット、ネットスーパーの活用もおすすめです。
「贅沢」ではなく、時間と心の平穏を買うための「投資」と考え、家事を外注しましょう。
家事育児の負担が偏る「ワンオペ」状態が、しんどさの大きな原因です。
大切なのは、パートナーに「手伝ってもらう」意識ではなく、「一緒に責任を持つ」意識を共有することです。
まずは「名もなき家事」も含め、すべてのタスクを「見える化」し、冷静に分担を決めましょう。
また、一度任せたら、お互いに相手のやり方へ口出ししないことも重要です。責任を持って担当する仕組みを作りましょう。
家庭内を改善しても「しんどい」なら、働き方自体が合っていない可能性があります。まずは社内制度の活用を確認しましょう。
「時短勤務」や「フレックスタイム」「リモートワーク」で物理的な負担を減らせないか相談してみてください。
もし、今の職場で調整が難しいなら、「転職」も一つの解決策です。
ワーママの働き方に理解があり、柔軟な制度を持つ環境へ移ることで、しんどさが根本的に解決する場合もあります。

フルリモートとは、週に数回の在宅勤務とは異なり、原則として出社を前提としない働き方です。
もちろん、高い自己管理能力が求められるなど、特有の難しさは存在します。
しかし、「しんどい」状況を打破し、自分らしいキャリアを継続したいと願うワーママにとって、フルリモートは最も強力な選択肢の一つです。
フルリモート最大の利点は「通勤時間ゼロ」です。もし往復で1時間半かかっていたなら、週に7時間半もの時間が生まれます。
この「時間的余裕」が、朝の戦場のような慌ただしさを解消します。
「会社に間に合わない」という焦りや、満員電車のストレスから解放される精神的・体力的メリットは計り知れません。
夕方も、仕事を終えてすぐ家事に取り掛かれたり、保育園のお迎えに余裕ができたりと、「心の余白」を生み出します。
フルリモートは「場所」と「時間」の制約から解放されるため、家庭の都合に合わせて仕事が組み立てられます。
たとえば、自宅で働けるため、子どもの体調不良時にそばで見守ったり、学童からの帰宅を「おかえり」と迎えたりできます。
また、場所の制限なく働けるため、パートナーの転勤でキャリアを諦める必要もありません。
さらに、フレックス制度や「中抜け」が可能なら、日中の授業参観や病院の付き添いなどで一時的に離席し、夜に業務を再開するといった柔軟な働き方ができます。
「育児中は簡単なパートしか選べない」というのは過去の話です。現在、IT、マーケティング、人事、経理など、専門職のフルリモート求人は数多く存在します。
これにより、ワーママが培った経験やスキルを、出産・育児を理由に手放す必要がなくなりました。
育児のためにキャリアを「中断」したり「ランクダウン」させたりするのではなく、働く場所を変えるだけで「継続」できる。
この「スキルの継続性」が、将来の収入不安を解消し、ワーママの自信を支えてくれます。
フルリモートはキャリアの「維持」だけでなく「アップ」も目指せます。
多くの企業では評価基準が「オフィスにいた時間」から「実際に出した成果」にシフトしており、場所に関わらず、成果を出せば正当に評価されます。
むしろ、通勤時間がなくなった分を新しいスキルの学習に充てるなど、主体的に市場価値を高めることも可能です。
また、リモートワークで培われる「的確な伝達能力」や「自己管理能力」は、どこでも通用するスキルです。「育児中だから」と諦めず、成長を続ける道を選べます。
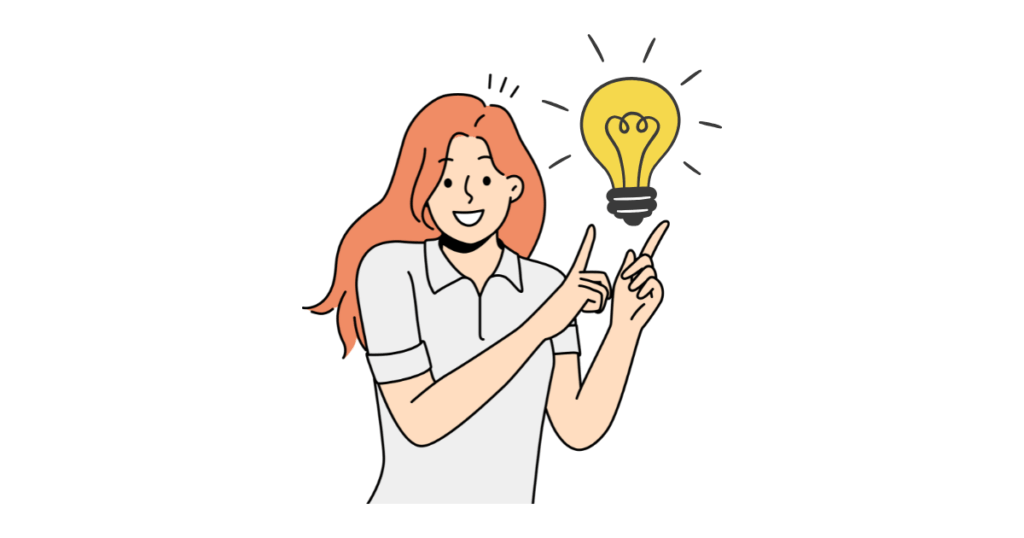
フルリモートは、多くのワーママにとって理想的な働き方であるため、仕事を探すのが難しいという現実があります。とくに、育児との両立を前提とした場合、条件に合う求人を見つけるには「コツ」が必要です。
フルリモートは目的ではなく、あくまでワーママがキャリアも家庭も諦めずに、自分らしく働くための「手段」です。
ここでは、その理想の手段を手に入れるための、具体的な3つのステップを解説します。
「フルリモート」と一口に言っても、求めるものは人によって異なります。通勤時間をゼロにしたいのか、それとも働く時間を自分で管理したいのか。まずは、求める条件を明確にしましょう。
正直なところ、多くのワーママが希望する「正社員」かつ「フルリモート」で、さらに「育児に理解がある」という求人は、市場全体で見るとまだ多いとは言えません。派遣社員でも、フルリモート案件は限られているのが実態です。
そこで、雇用形態の前提を一度見直してみることをおすすめします。それが「フリーランス(業務委託)」という選択肢です。
フリーランスであれば、会社に時間で拘束されるのではなく、スキルや成果物に対して報酬が支払われます。そのため、企業側と対等な立場で「フルリモート」を前提とした契約を結びやすいメリットがあります。
正社員という枠にこだわりすぎず、フリーランスという働き方を視野に入れることが、結果として、ワーママの理想とする「柔軟な働き方」への近道になるかもしれません。
理想の働き方として「フリーランス × フルーリモート」を視野に入れた場合、次に不可欠となるのが「自分の得意なこと=強み」を正確に整理することです。
「自分には特別なスキルなんてない」と思い込む必要はありません。まずは、これまでの職務経歴を棚卸ししてみましょう。
たとえば、「経理事務をしていた」という経験は、「クラウド会計ソフトfreeeを使った月次決算作業ができる」「請求書発行から入金消込まで、一人で完結できる」といった具体的なスキルに分けられます。
こうした一つひとつのスキルが、企業が「リモートで任せたい業務」と合致する可能性があります。
ワーママが育児や家事の合間に、膨大な求人情報の中から「理想のフルリモート案件」を一人で探し出すのは、大変な労力が必要です。
そこでおすすめしたいのが、プロの力を借りる「エージェント」への登録です。エージェントは、あなたのスキルや希望条件をヒアリングした上で、非公開案件を含む多くの選択肢の中から最適な仕事を紹介してくれます。
とくにフリーランスの案件探しにおいては、面倒な条件交渉や契約手続きを代行してくれるため、ワーママは安心して業務に集中できるメリットもあります。
たとえば、フルリモート専門のエージェント「キャリモ」のようなサービスでは、ワーママの状況を熟知したキャリアアドバイザーが、スキルを活かせるフリーランス案件や柔軟な働き方が可能な求人を提案してくれます。
まずは登録して、自分の経歴でどのようなフルリモートの「選択肢」があるのか、プロの視点からアドバイスをもらってみるのもおすすめです。
ワーママの「しんどさ」のピークは一度ではなく、乳幼児期の「体力的」なものから、学童期の「時間管理・精神的」なものへと形を変えて続きます。この長い戦いを乗り越えるには、完璧主義を手放す工夫や、家事の時短、パートナーとの分担が欠かせません。
しかし、日々の工夫だけでは限界があり、「しんどい」状況を根本から変えたいと願うなら、「働き方」そのものを見直すことが大切です。
とくに、通勤時間がなく、育児のスキマ時間も活用しやすい「フルリモート」という働き方は、ワーママがキャリアを諦めずに自分らしく輝くための大きな可能性を秘めています。
ぜひ一度、フルリモート専門エージェント「キャリモ」に相談してみませんか?あなたの経験やスキルを棚卸しし、理想の働き方を実現できる選択肢を一緒に探してくれます。